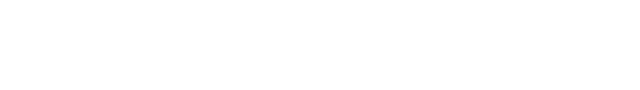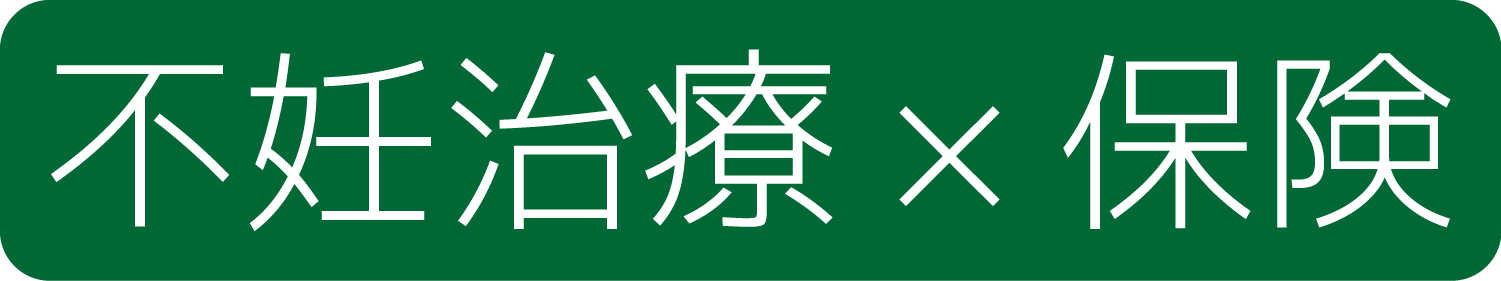不妊治療と仕事の両立のために
不妊治療に関する助成金ですが、職場環境を整備することで事業主(会社)が助成を受けられるものがあります。
- なぜ、両立支援が必要なのでしょう?
- 支給対象となる事業主
- 支給要件
- 支給額
- よくある質問
- 社内ニーズ調査」とは
- 両立支援担当者とは
- 不妊治療両立支援プランとは
- 参考資料
- 他にも使える助成金が
なぜ、両立支援が必要なのでしょう?
不妊治療を経験した方のうち16%(男女計[女性は23%])が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しています。
両立に困難を感じる理由には、通院回数の多さ、精神面での負担の大きさ、通院と仕事の日程調整の難しさがあります。
労働者の中には、治療を受けていることを職場に知られたくない方もいます。
職場内では、不妊治療についての認識があまり浸透していないこともあります。
⇒ 企業には、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の
整備が求められます。
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)
支給対象となる事業主
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を導入し、実際に不妊治療を行う労働者がこれらの制度を利用させた場合に助成金が支給されます。
- 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
- 所定外労働制限制度
- 時差出勤制度
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制
- テレワーク
支給要件
- 不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
- 整備した上記の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
- 不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任
- 「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定
支給額
A.「環境整備、休暇の取得等」
支給要件の全てを満たし、最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
1中小企業事業主:28.5万円
B.「長期休暇の加算」
上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1中小企業事業主:28.5万円(※1事業主当たり1年度に5人まで)
なお、生産性要件を満たす場合は支給額が36万円となりますので、詳しくは、支給要領をご確認いただければと思います。
両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)についてよくある質問
「社内ニーズ調査」とは何でしょうか?
不妊治療と仕事の両立に関して、労働者が求めている制度や支援策について把握するためのものです。新たにアンケート調査を実施することや、既に実施している自己申告制度を活用することが考えられます。
両立支援担当者とはどういう方が当てはまりますでしょうか?
人事労務担当者や産業保健スタッフ等が考えられます。不妊治療を受ける労働者の相談に対応し、労働者一人ひとりの「不妊治療両立支援プラン」を策定し支援する者として事業主に選任されていれば、資格や役職などは問いません。
厚生労働省では、人事労務担当者向けのマニュアルを周知しています。ご活用ください。
不妊治療両立支援プランとはどういうものでしょうか?
両立支援担当者が、不妊治療を受ける労働者から利用したい制度・働き方の希望などを聴いた上で、制度の利用予定、その間の業務分担の見直し等の検討も含め、治療と両立しやすい環境整備を図るために策定するプランです。
職場内での不妊治療への理解を深めていただくため、ご活用いただける、不妊治療の内容や職場での配慮ポイントなどを紹介したハンドブックもあります。
【参照】不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)
不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合は、以下の助成金も活用できます。
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」
支給対象となる事業主:不妊治療等のために利用できる特別休暇制度(多目的・特定目的とも可)を導入した中小企業事業主
対象経費:外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更などの休暇制度の導入に関する経費
支給額:上限50万円(所得経費の3/4。一定の要件を満たした場合4/5)